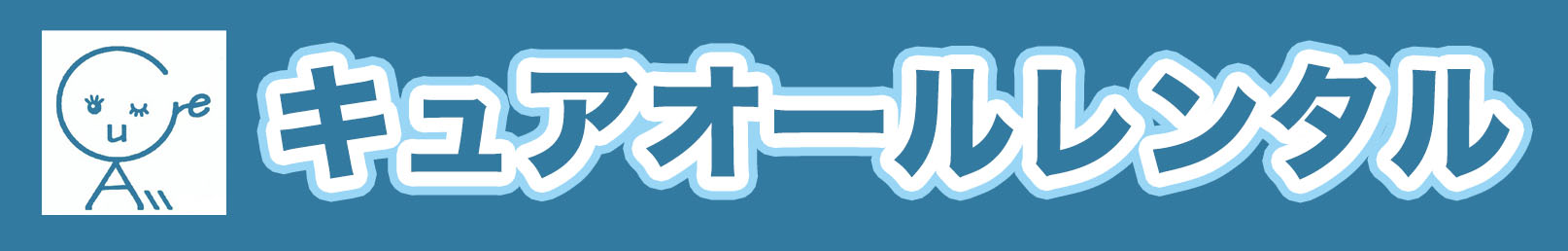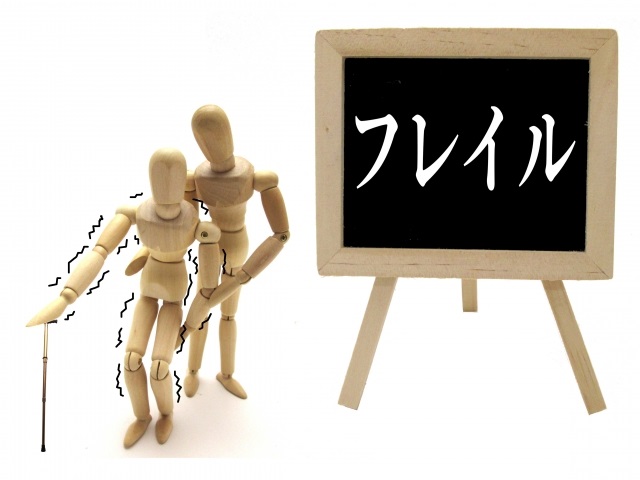こんにちは、キュアオールレンタルです。
車椅子や要介護の方が利用できる「介護タクシー」「福祉タクシー」
利用方法・料金・サービス内容をご紹介します。

要介護の方や体が不自由な方が安心して利用できるタクシーです。
【特徴】
●車椅子やストレッチャーに乗ったままで乗車可能
●介護の資格を持つ運転手が、乗降介助
●介護保険が適用される
*資格を持つ運転手の「通院等の乗降介助」サービスです。
【注意】
資格がない運転手は、利用者から「介助」を頼まれても法律上できません
「福祉タクシー」は要介護の方専用の車両で、運転手は無資格で乗降介助できない
【特徴】
●介護保険は適用されない
●乗降時のサポートが必要な場合は、家族等が付き添う
●リフトやスロープがついたワンボックスカー
●車椅子から助手席への移乗がしやすいよう助手席のシートが90度回転
●ベッドで乗降できる寝台車もある

介護タクシーは訪問介護サービスで、利用できる人と目的が決まっています。
【利用対象者】
介護保険の要介護認定で「要介護1」以上で、ひとりで公共交通機関を利用できない方
*要支援1~2の方は利用できません。
【利用目的】
「日常生活または、社会生活で必要な行為に伴う外出」のみ
・通院
・補聴器や眼鏡など本人が現場に行く必要のある買い物
・預貯金の引き出し
・選挙への投票
・役所に届け出をする等
上記以外のプライベート目的では、介護保険を使った介護タクシー利用はできません
受けられるサービスは、訪問介護の「通院等の乗降介助」です。
【通院する場合の具体例】
①外出準備介助・・着替えや靴を履くなど
②移動と乗車降車介助・・室内から病院まで
③病院での受付、会計、薬の受け取り
④移動と乗車降車介助・・病院から室内まで
⑤着替えの介助やおむつ交換(必要な場合)
*介助の範囲は、ケアマネジャーと相談して決めます
*要介護1以上でも「介助なしで車両に乗降できる」場合は、介護タクシーは利用できません
●ケアプランに記載ないサービスは受けられない
●利用者と事業者の契約が必要
●家族は同乗できない
●病院内での介助しない(例外的に介助が認められることもある)
⇒病院内は看護師が担当
●介助量が増えると「身体介護」や「生活援助」となり費用が変わる
①ケアマネジャーに相談
利用可能かケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、ケアプラン作成
![]()
②介護タクシー事業者と契約
料金・予約方法・支払い方法等を確認し契約する
![]()
③利用内容、同乗者日程を決める
利用日程が決まれば、介護タクシーを予約
![]()
④当日の利用
利用料金は「運賃」「介護サービス費」「車椅子など介護機器のレンタル費」を合計した金額で、介護保険が適用されるのは「介護サービス費」だけです。
実費の料金は事業者ごとに違うので、事前に複数の事業者と料金を比較し確認しましょう。
【運賃の計算方法の例】
「時間制」と「距離制」のどちらかで計算されます。
時間制運賃・・「30分ごとに1,000円」「最初の30分が600円、以降は30分ごとに1,500円」
距離制運賃・・「最初の2キロ800円、以降は1キロごとに400円」など
*距離制運賃は、一般のタクシーと同水準のメーター料金設定が多い
【介護器具レンタル料の一例】
・車椅子 500円~
・ストレッチャー 4,000円~
・酸素吸入セット 3,000円~
家族と本人が納得できる事業所を見つけるには、しっかりと状況や要望を伝えましょう。
介護タクシー事業所を選ぶ時は担当のケアマネジャーと「料金設定が妥当か」「運転者のスキルや人柄に問題がないか」を検討しましょう。
料金は事前に見積もりを出してもらいチェックすることが重要です。
介護の負担を減らすためにも、介護タクシーの利用を上手に活用してください。